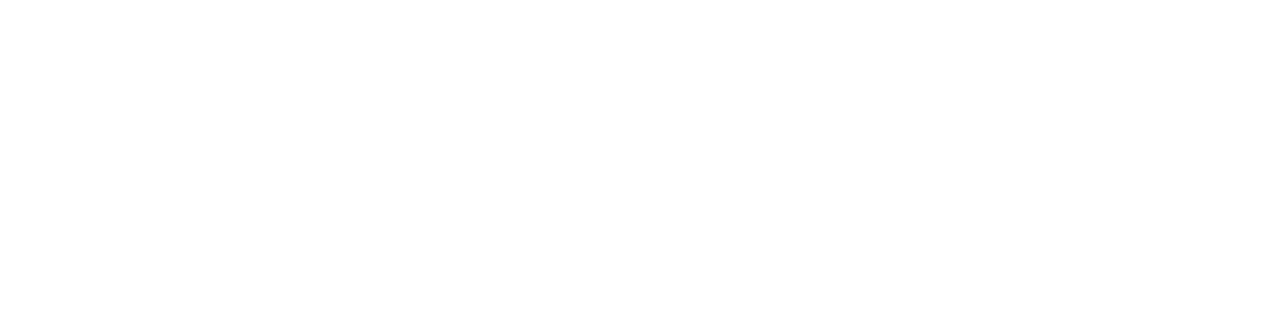皆様こんにちは、ネットワーク事業部の浅井です。
今回は、業務上取り扱うデータを共有したり保存したりするのに欠かせないNASについて、BUFFALO製とI-O DATA製にフォーカスして、独自OS版とWindows Server版でどういった違いがあるのかを紹介いたします。
なお、今回の記事に記載された内容について、他メーカー製のNASは仕様が異なる場合がございます。
他メーカー製品に関する詳細はメーカーサイトをご確認ください。
独自OS版とは?
導入でも触れましたが、BUFFALO製とI-O DATA製の法人向けNASには独自OS版とWindows Server版が存在しています。
まず、独自OS版について簡単に解説していきます。
独自OS版とは、メーカーが独自に開発したLinuxベースのOSを搭載したモデルのことを指します。
特徴としては、NAS用に最適化されているため安定性に優れていたり、複雑な操作が不要でシンプルなWeb UIから共有フォルダ作成やユーザ作成、権限等を設定することが可能です。
NASに関してあまり詳しくなくても、比較的利用しやすい製品となっています。
Windows Server版とは?
分かりやすいようにWindows Server版と記載しましたが、正確には、Windows Storage Serverを搭載した製品を指します。
Windows Storage Serverとは言いますが、多少の表示項目や機能に違いがあるものの基本的には通常のWindowsと変わりません。
そのため、Windowsの操作になれた方にとっては扱いやすい製品となっています。
また、独自OS版に比べると自由度が高いため、複雑な設定や構成も組むことが出来ます。
独自OS版のメリット・デメリットについて
メリット
■低コスト
Windows Server版に比べると、自社開発のOSを利用しておりライセンス費用が不要であるため、価格が安い
■設定・運用が簡単
Webベースの管理画面が用意されており、ITスキルが無くても設定や管理をすることができる
■安定性に優れている
NAS以外の機能が省かれているため、動作不良が起きにくい
デメリット
■細かい権限設定や設定調整に制限がある
あらかじめ機能を作り込んでいる環境のため、サブフォルダの共有権限設定などに対応できない機種も多い
■拡張性に乏しい
独自OSで動作しているため、サードパーティ製のソフト等を利用することができない
■セキュリティに関しての選択肢が少ない
BUFFALO、I-O DATAともに、NASが対応している専用のウイルス対策機能のみ導入可能で、オプション契約となるため追加費用が必要な場合が多い
こんな方におすすめ
ITの専門知識が無くても直感的な管理画面からすぐに運用を始めることが出来るため、専任の担当者がいないような小・中規模のオフィスにおすすめです。
Windows Server版のメリット・デメリットについて
メリット
■権限設定や設定調整に柔軟性がある
サブフォルダ単位での権限設定など、独自OS版よりも細かい部分の設定調整が可能
■Active Directoryとの連携に優れている
Windows Serverと同等の機能を有しているため、独自OS版は対応できないActive Directoryのグループポリシーを適用する等が可能
■拡張性に優れている
独自で、サードパーティ製のソフトやウイルス対策ソフトをインストールすることが可能
Windows Serverに搭載されているIIS(Webサーバー機能)等も利用可能
■バックアップ機能に優れている
Windows Serverに搭載されている『Windows Serverバックアップ』機能を用いることで、OS含めてバックアップをすることが可能
サードパーティ製のクラウドバックアップシステム等も利用可能
デメリット
■高コスト
独自OS版に比べると、Windowsライセンス費用が必要であるため、価格が高い
■運用管理にWindowsやWindows Serverの知識が必要
共有フォルダの作成や、権限設定をするだけでもWindowsの知識が必要
多くの機能が搭載されているものの利用するためには多くの知識が必要となる
■Windowsアップデートが必要
独自OS版に比べると頻繁にWindowsアップデートが配信されるため、定期的な管理作業が必要
こんな方におすすめ
部署や人員毎に、多くの階層に跨ったアクセス権限を設定したい、サードパーティ製ソフトを独自に導入してカスタマイズしたい、といった高度な運用管理や拡張性が求められるオフィスにおすすめです。
NASのバックアップについて
独自OS版
■外付けHDDへのバックアップ
NAS本体の背面からUSB経由で外付けHDDにバックアップを行います。
バックアップ設定はWeb管理画面から設定し、バックアップ対象や実施スケジュールの設定が可能です。
基本的にデータのみのバックアップのため、本体が故障した場合にデータまで損失しないための措置です。
■同一ネットワーク内のNASへのバックアップ
同一ネットワーク内にNASを設置し、予備機としてバックアップ機能を利用し同期を取ります。
バックアップの設定方法は基本的に外付けHDDと同様ですが、メイン機が故障した場合に『デバイス名』と『IPアドレス』を変更すれば最後に同期した状態からNASの運用を再開することができます。
障害発生から復旧までが一番早いため、NASの故障によって業務を止めたくない場合には是非導入したいバックアップ構成です。
■メーカー提供のクラウドバックアップサービス
BUFFALOは『キキNaviクラウドバックアップ』、I-O DATAは『NarSuSクラウドバックアップ』というサービスをそれぞれ提供しています。
取得したデータはメーカーの管理するデータセンターにバックアップされます。
NASの設定情報等も含めてクラウドにバックアップすることが可能です。
バックアップは世代で管理され、任意のバックアップスケジュールに従ってバックアップが取得されます。
(毎日、もしくは週の任意の曜日の任意の時間に実行)
データの削除は任意の日数経過後に削除する設定が可能です。
(BUFFALOの場合は最大90日後)
データ復元の際は、NAS上の任意のフォルダにデータを復元することが可能です。
Windows Server版
■外付けHDDへのバックアップ
NAS本体の背面からUSB経由で外付けHDDにバックアップを行います。
サーバー管理ツール『Windows Server バックアップ』を利用することで、NAS全体のバックアップが可能です。
また、サードパーティ製のバックアップツールを利用し、外付けHDDにバックアップすることも可能です。
■同一ネットワーク内のNASへのバックアップ
独自OS版と同様に、同一ネットワーク内にNASを設置し、予備機としてバックアップ機能を利用し同期を取ります。
同期処理には、Windowsの機能を用いて同期プログラムを作成したり、サードパーティ製のツールを利用する等の工夫が必要のため、独自OS版に比べると高度な技術が必要になります。
■メーカー提供のクラウドバックアップサービス
独自OS版と同様に、『キキNaviクラウドバックアップ』、I-O DATAは『NarSuSクラウドバックアップ』というサービスが利用可能です。
基本的には独自OS版と同様のバックアップの設定が可能となっています。
データ復元も同様に、NAS上の任意のフォルダにデータを復元することが可能です。
■サードパーティ製のクラウドバックアップサービス
独自OS版との違いとして、メーカー提供以外のクラウドバックアップサービスを利用することが可能です。
メーカー提供のクラウドバックアップサービスの場合、バックアップ方式や復元方式、スケジュール設定等が利用者の要望とマッチしない場合も多々あります。
Windows Server版であれば、該当環境で稼働するクラウドバックアップサービスは多く存在するため、最適なサービスを選択、導入することが可能です。
WideNetクラウドバックアップ
弊社では、NASにご利用いただけるクラウドバックアップサービスを提供しております。
データの保存先は、弊社提携の国内データセンターとなっております。
メーカー提供のクラウドバックアップサービスと比較すると、より柔軟なスケジュール設定や、バックアップ期間の設定、バックアップの稼働条件等、ご利用環境に合わせたカスタマイズに対応することができます。
また、データの復元の際も、任意の端末に対してファイル・フォルダ単位での復元が可能となっており、NASが故障してしまった場合でも新品のNASを用意することなく早急なデータの取り出しが可能となっております。
興味がございましたら、問合せフォームから問合せいただけますと幸いです。
まとめ
今回は、BUFFALO製とI-O DATA製のNASに絞ってそれぞれのOSのメリット・デメリットについて紹介しました。
それぞれのOSによって、特徴や強みがありますのでご自身のオフィスに合わせたNASを検討する際に役立ていただければと思います。
弊社では、NASの導入やリプレイスのご相談も随時受け付けておりますので、こちらからお気軽にお問合せ下さい。
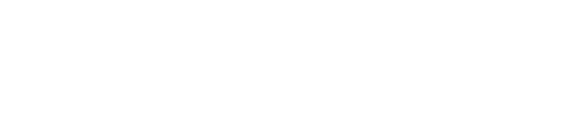



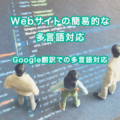
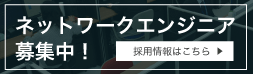
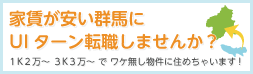
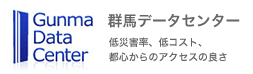
![群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット] 群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット]](https://www.nedia.ne.jp/wp-content/themes/nedia/images/bnr_bt_widenet02.png)



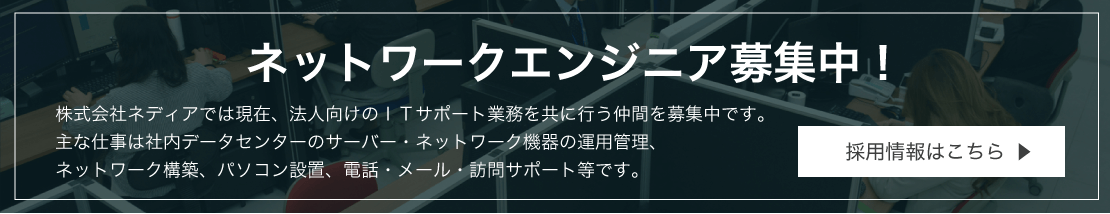
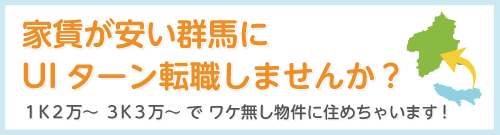
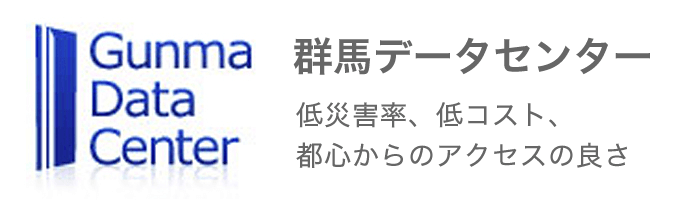
![群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット] 群馬の法人ITサポートサービス Wide Net[ワイドネット]](https://www.nedia.ne.jp/wp-content/themes/nedia/images/bnr_bt_widenet03.png)